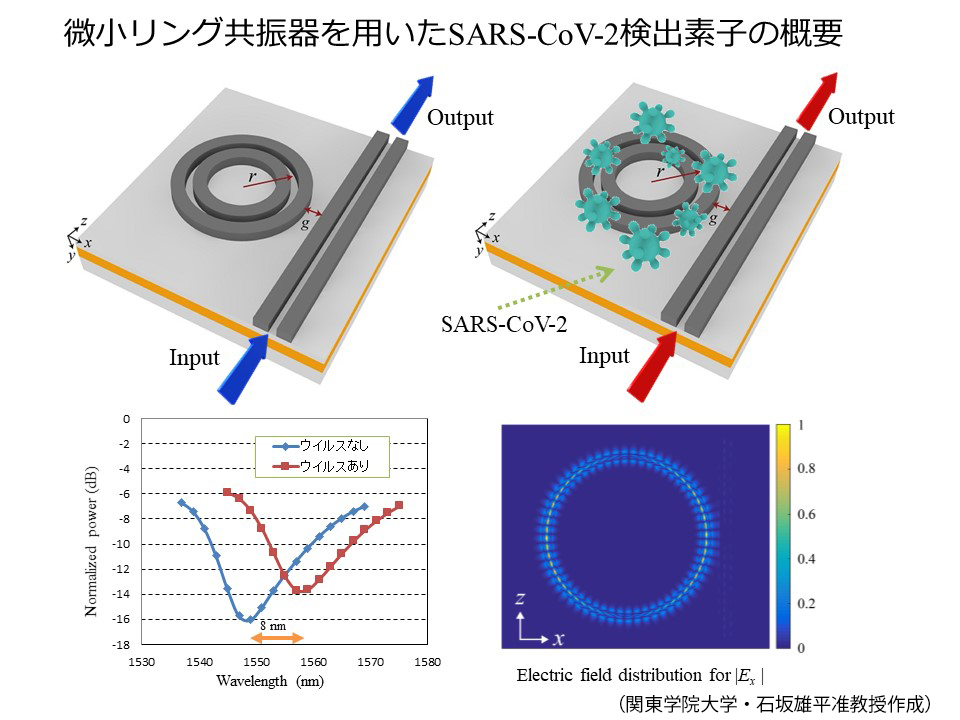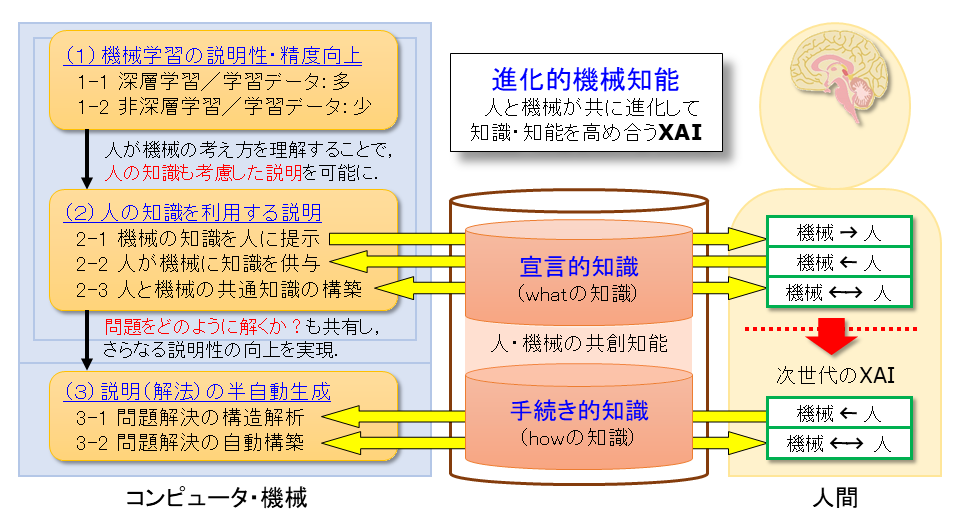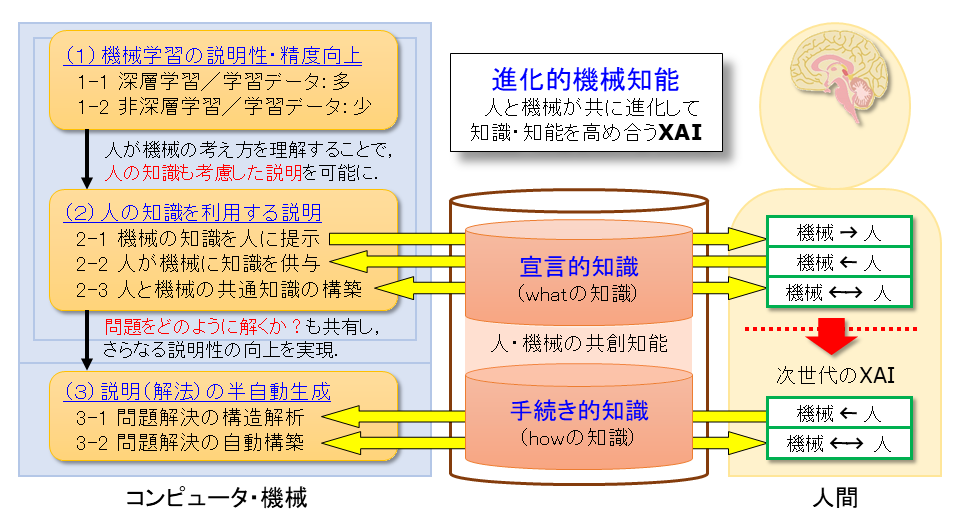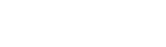【活動概要】
中央社会保険医療協議会では、公益委員として新型コロナウィルス感染症に伴う医療保険制度の対応を協議しており、例えば、レムデシビルの医療保険上の取扱いなどを検討しました。中医協の協議内容については、次のウェブサイトをご参照ください。
中央社会保険医療協議会(中央社会保険医療協議会総会)
新型コロナウィルス感染症は、もっともか弱いバルネラブル(脆弱)な人たちを苦境に立たせています。例えば、高齢者については、介護を受けられる環境を失い、とりわけ海外においては高齢者関連施設が多くの死者を出しているのみならず、人工呼吸器を装着する順番が年齢により決められました。
主宰するYNU成熟社会コンソーシアムでは、withコロナ時代、ニューノーマルな社会において、年齢差別のない社会、障がい者といったバルネラブルな人たちをめぐる課題、テレワークといった新しい働き方、採用のあり方などについて、様々な研究者とともに研究しています。
YNU成熟社会コンソーシアムとは、横浜国大を中心に文系・理系を問わず多様な研究者が集まり、成熟社会をめぐる課題について文理融合研究をする集まりです。
Involved in policy making concerning COVID-19.
At the Central Social Insurance Medical Council, as a public interest member, I am involved in the discussion concerning the way to deal with COVID-19 in the National Health Insurance system.
At the YNU Seijyuku Society Consortium, we discuss about the society with COVID-19 and post-pandemic New Normal society. Integrated scholars of arts and sciences of YNU discuss about age discrimination, issues concerning most vulnerable people such as disabled person, the new way to work such as remote work and so on.
Japanese term "Seijyuku" society means mature society, the next society that is diversified and integrated.
COVID-19 put vulnerable people into difficult situations. For example, the elderly not only are at higher risk for developing more serious complications from COVID-19, they are at the risk of losing the lives in nursing homes in some countries. They also lost care environments at home and facilities. Moreover, some countries have prioritized younger over older patients in using intensive care unit beds, ventilators and other medicines. Not only their underlying illnesses, but the age became the indicator in prioritizing the use of medical resources. Even when there could be an 80 years old who live 10 or 20 more years, and an 50 years old who could not live for 10 more years. The age-related rationing discriminate the elderly only because they are old. Lots of underlying problems became clearer with the COVID-19 pandemic and YNU Seijyuku Society Consortium discuss about these issues.