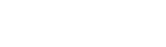【プレスリリース】阿寒湖のマリモ、生物量が過去120年で大きく減少
発表のポイント
・国の特別天然記念物「阿寒湖のマリモ」の過去の生物量を湖底堆積物に残存するDNA(環境DNA)とミジンコ遺骸を用いて推定しました。
・堆積物中のマリモDNAは時間とともに分解し減衰していましたが、同じ堆積物に含まれるミジンコの遺骸とDNAを用いてDNA分解速度を算出して補正する方法を開発した。
・その結果、120年前までは現在の10~100倍だったマリモの生物量は、20世紀前半の森林伐採や水力発電用取水が著しかった時期に大きく減少し、マリモの生育に土砂流入や水位変動が大きな脅威であったことがわかりました。
概要
「阿寒湖のマリモ」(学名: Aegagropila brownii)は、球状集合体を形成する緑藻で、20世紀前半にその生物量が減少したとされてきましたが、生育状況の変遷を示す定量的なデータはありませんでした。 占部城太郎(東北大学大学院生命科学研究科名誉教授・横浜国立大学総合学術高等研究院客員教授)をリーダーとする東北大学、釧路国際ウェットランドセンター、神戸大学、愛媛大学の共同研究チームは、底堆積物に残存するマリモのDNA(環境DNA)を用い、過去200年前から現在に至るマリモの生物量の変遷を明らかにしました。ミジンコの遺骸とDNAを利用して時間経過によるDNAの分解速度を補正する手法を開発して分析したところ、1900年初頭のマリモの生物量は現在の10~100倍も多く、その後の数十年間でマリモの生物量は大きく減少し、阿寒湖周辺の森林伐採による土砂の流入や水力発電の影響による水位変動が、マリモの生育環境に大きな影響を与えたことがわかりました。
また、1950年以降は観光化による阿寒湖の富栄養化が生育状況の回復を妨げていた可能性も示されました。本研究成果は、観光資源としても重要なマリモの保全策立案のみならず、遺骸や化石を残さない生物の過去の生息・生育密度を復元する新たな手法として、生態系の保全や生物多様性の目標設定および再生に活用されることが期待されます。
本研究成果は2025年3月31日に国際誌Environmental DNAで公開されました。
論文情報
| 掲載誌 | Environmental DNA |
|---|---|
| タイトル | Reconstruction of marimo population dynamics over 200 years using molecular markers and fossil plankton remains |
| 著者 | Jotaro Urabe, Isamu Wakana, Hajime Ohtsuki, Masayuki K. Sakata, Yurie Ohtake, Ryotaro Ichige, Michinobu Kuwae, Toshifumi Minamoto *責任著者:東北大学大学院生命科学研究科 名誉教授 占部城太郎 |
| DOI | https://doi.org/10.1002/edn3.70085 |
資料
お問い合わせ先
<報道に関すること>
高等研究院 研究戦略企画チーム
メールアドレス: ias-ims ynu.ac.jp
ynu.ac.jp
(担当:リレーション推進課)